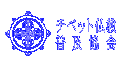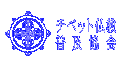|
現在の「国」という国際法的な概念は、20世紀の初めに西洋から生じたものである。19世紀中頃の東洋、とりわけチベットについていえば、西洋的な「国」という明確な概念をもっていなかった。だから当時の人は、ここが国境であるとか、隣人が、実は他国の国民であるとか考えても見なかっただろう。ヒマラヤの国々、チベットもネパールもブータンでも、人々は自由に行き来し、互いの土地に親戚関係があって、国が出したパスポートの写真でアイデンティティを決めるということはなかったのだ。したがって、中国の「チベットは、何時いつに中国の一部になったのだ」という主張の根拠は、双方にとって歴史的証明が不可能なことで、双方が一つのテーブルについて主張しあったら整理のつかないことだと、私は思う。
両国は「国」という感覚のもとに交わっていたのでも、戦っていたのでもなく、あえていえば、民族間あるいは共同体間にいろいろな問題が発生したのであり、そういう意味では、現在の「国」としての中国とチベットの関係を規定するのに、昔のチベットの歴史を遡って根拠を求め、あれこれ論じるのは意味をなさない。
ただ、なぜ、現在、ダライ・ラマ法王がインドにあって、なにゆえ中国がチベットを自治区とし、なぜラサで暴動がおきているのかを理解しようとするならば、その背景として19〜20世紀初頭の植民地主義・帝国主義を念頭におく必要がある。それこそが、そういった状況をつくりだすにいたった概念の基礎を形づくるものだからである。
 18〜19世紀、ヨーロッパでは科学と技術が発展し、経済力がまし、政策も社会状況も変ってきた。特にイギリスは、インドをはじめとしてアジア諸国を植民地化し、市場とするためにアジアに入ってきた。当時チベットをめぐってロシア・中国・イギリスが互いに牽制しあいながらチベットに入ろうとしていた。三国にとってチベットは地理的・戦略的に好都合だという理由で、チベットをめぐってせめぎあい、ときに相手を阻止するために、他の二国が妥協して手を結ぶなどの策略を巡らしたりもした。
18〜19世紀、ヨーロッパでは科学と技術が発展し、経済力がまし、政策も社会状況も変ってきた。特にイギリスは、インドをはじめとしてアジア諸国を植民地化し、市場とするためにアジアに入ってきた。当時チベットをめぐってロシア・中国・イギリスが互いに牽制しあいながらチベットに入ろうとしていた。三国にとってチベットは地理的・戦略的に好都合だという理由で、チベットをめぐってせめぎあい、ときに相手を阻止するために、他の二国が妥協して手を結ぶなどの策略を巡らしたりもした。
例えば、1890年にイギリスと中国(清王朝)のあいだに条約(CONVENTION)が結ばれたが、これはダライ・ラマ13世と深いつながりを持つモンゴルを利用してのロシアの接近を阻止するためのものだった。当時、チベットは、中国の侵略を防ぎ西洋のキリスト教から仏教を守るため頑固に国を閉ざしていたが、イギリスの軍隊は度々チベットに侵入し、1904年にはチベットとの間で、両国の合意なしには他の国をチベットにいれないこと、西チベットに貿易センターを作ってもよいが軍事力をできるだけ少なくすることなどのラサ条約が、両国の間で結ばれた。このことはチベットから見れば、条約の内容は別にして、当時チベットが条約を結べる独立国であったという証明にもなる。
1906年には、再びチベット抜きでイギリスと中国が条約を結び、1914年には北インドのシムラでシムラ条約をむすんだ。シムラ条約も、当時チベットが独立国であったことを示している。
ダライ・ラマ13世は優れた政治的な感覚をもっておられ、イギリスだけでなくロシアとも話し合ったり、1908年には北京で日本政府の要人ともあい、ラサに招いたりしている。しかし、その間のダライ・ラマ13世の努力は、残念ながら全国民的なものとはならなかった。ダライ・ラマ13世は、1934年に亡くなったのだが、中国は、その葬儀に参列するという名目で、代表を送り込み1904年以来、ラサから締め出されていた代表部を再会した。
 第二次世界大戦後に、帝国主義は弱体化しイギリスは撤退して、100年ほど植民地状態だったインドは独立国となった。ロシアは、1917年のロシア革命で昔からの皇帝独裁主義をはなれ、共産主義への道をたどり軍事力を強めてヨーロッパやアジアと戦火を交えた。そしてアメリカとの冷戦が始まる。中国は、貧富の差などの社会問題が悪化し、その解決の手だてとして共産主義を生み出した。第二次大戦後日本が中国から手を引くと、共産主義が勢いを増し、内戦の結果、敗れた国民党は台湾へ逃げることになり、中華人民共和国が誕生した。チベットは、これらの三国に囲まれて、仏教にもとづいて平和主義を貫き、自立した在り方を堅持しようとしていた。
第二次世界大戦後に、帝国主義は弱体化しイギリスは撤退して、100年ほど植民地状態だったインドは独立国となった。ロシアは、1917年のロシア革命で昔からの皇帝独裁主義をはなれ、共産主義への道をたどり軍事力を強めてヨーロッパやアジアと戦火を交えた。そしてアメリカとの冷戦が始まる。中国は、貧富の差などの社会問題が悪化し、その解決の手だてとして共産主義を生み出した。第二次大戦後日本が中国から手を引くと、共産主義が勢いを増し、内戦の結果、敗れた国民党は台湾へ逃げることになり、中華人民共和国が誕生した。チベットは、これらの三国に囲まれて、仏教にもとづいて平和主義を貫き、自立した在り方を堅持しようとしていた。
世界で資本主義と社会主義の戦いがまきおこるなか、毛沢東はインドにまで共産主義を広めようと、1950年、チベットに中国軍を進めた。その後の10年間にわたりチベットは平和的解決のため話し合ったが話は通じない。彼らはチベットを近代化し教育や鉄道建設などに協力するといい、我々は仏教国として自分たちなりにするという主張で結果はでなかった。その頃イギリスはすでに勢力を拡大することをやめ、自国に戻っていたため興味を示さず、ソ連は中国に同調して見て見ぬふりをした。また、隣国インドは独立直後のため力不足であった。それまでチベットをめぐって関係していた国々は諸事情から関わりをもたなかったため、チベットは自力で中国と交渉を続けざるをえなかった。
中国との交渉に成果はなく、チベットの採る道は、戦うか逃げるかしかなかったが、ダライ・ラマ14世は「僧侶であるから暴力は使わない。殺戮はいかなる動機に基づくものであってもなすべきではない」という信条により、逃げる道を選ぶのである。政治はよく宗教を利用するものだが、チベットではそうではなく、「人が人を殺してはいけない」という仏教の教えが基本にあったのである。それは難しい決定だった。後に残す大勢の人が中国に虐待されないか、亡命しても、将来どのように道が開けるのか、さまざまな状況で人間の知恵では判断できないことが多かった。
中国は、ダライ・ラマひとりがいなくなればチベットは簡単だと思って、イベントを催してダライ・ラマを招待しそのまま北京に連れていこうとした。それを察知したチベットの人々は、ダライ・ラマを守ろうと宮殿を3万人の人が囲んだ。ここで3月10日の暴動が起きたのである。
チベットには武器もなく人口も少なく、中国と戦うのは自殺的な行為だったといえるだろう。しかしチベットは、人口は少ないが心はひとつ目的はひとつで、それはダライ・ラマを守る、仏教を守る、国を守るということだけだった。チベットのひとりの兵士は20人の中国の兵と戦うことができるのだ。自分が死ぬことはわかっていても、そのためになら戦うということが中国もわかっていたから、怖がって十年もかかったのだろう。
その夜、ダライ・ラマ14世はラサを脱出、あとを追った十万人の人々ともどもヒマラヤをこえたのである。そして、インドのネール首相の認可を得て、宗教・政治両面の指導者たるダライ・ラマ法王は、北インドの地、ダラムサラに未来のチベットのため、また逃亡してきたチベット人のために、自らの亡命政権を樹立した。
 亡命というのはゼロからの出発である。当初の十年は、逃げてきた十万人以上の人々の生活と、その子供たちの教育や民族文化のアイデンティティを守ることに費やされた。次の十年間の1970年代は、亡命生活の土台が築かれ、チベットについての事実を世界の人々に伝えるため、法王をはじめとして、さまざまな文化人達が西洋を中心に活動することにあてられた。その結果、80年代は、チベットの事情や法王の思想がある程度理解され、亡命チベット人達の平和主義の努力が世界中の人々に認められ、89年にはダライ・ラマ法王が、ノーベル平和賞を受賞された。
亡命というのはゼロからの出発である。当初の十年は、逃げてきた十万人以上の人々の生活と、その子供たちの教育や民族文化のアイデンティティを守ることに費やされた。次の十年間の1970年代は、亡命生活の土台が築かれ、チベットについての事実を世界の人々に伝えるため、法王をはじめとして、さまざまな文化人達が西洋を中心に活動することにあてられた。その結果、80年代は、チベットの事情や法王の思想がある程度理解され、亡命チベット人達の平和主義の努力が世界中の人々に認められ、89年にはダライ・ラマ法王が、ノーベル平和賞を受賞された。
90年代に入ると、チベット問題は国際的になり、アメリカでは、民間レベルから議会レベルへと格上げされて、現段階では経済問題とからめての人権問題について交渉などの具体策の検討にはいっている。
現在、チベット人は北京(中国)にすむチベット人、ラサなど本土にいるチベット人、外国にすむチベット人と三つにわけることができる。北京に住むチベット人は日常の暮らしのなかで、待遇などに民族差別を受け、現実的な問題から、一番はっきりとチベット人はチベットという国でなければ生きていけないと感じている。本土に暮らす人は中国の政策のもとで中国の人と交わり、ときに自分を欺きながらでもなんとか暮らしている。外国に住むチベット人はなにかをやってもその影響が中国まで届かない、という状態である。
 こうしたことは、チベットが何々をできなかったとか、中国が悪かったということよりも、政策をうみだした人間の欲望、簡単に人の命をもてあそぶ思想から出ている。国民主義とか帝国主義とか共産主義とか主張しあい、イデオロギーを社会にインプットして人々を動かしてきたのは、我々の過去の歴史の誤りだと思う。そのなかで、今一番悪い状況に置かれているのがチベットだと言えるだろう。しかし、つまるところ、このような逃れがたいかに見える世界の政治状況は、もとをただせば、清らかなはずの我々の心の曇りに起因しているのであり、心の内面の問題に取り組むということが我々の生きるこの現実にとってどれだけ重要かつ有用であるかを、一人でも多くの人に認識して欲しい。その結果、外面である世界は必ず変化を遂げるに違いない。
こうしたことは、チベットが何々をできなかったとか、中国が悪かったということよりも、政策をうみだした人間の欲望、簡単に人の命をもてあそぶ思想から出ている。国民主義とか帝国主義とか共産主義とか主張しあい、イデオロギーを社会にインプットして人々を動かしてきたのは、我々の過去の歴史の誤りだと思う。そのなかで、今一番悪い状況に置かれているのがチベットだと言えるだろう。しかし、つまるところ、このような逃れがたいかに見える世界の政治状況は、もとをただせば、清らかなはずの我々の心の曇りに起因しているのであり、心の内面の問題に取り組むということが我々の生きるこの現実にとってどれだけ重要かつ有用であるかを、一人でも多くの人に認識して欲しい。その結果、外面である世界は必ず変化を遂げるに違いない。
(終)
|