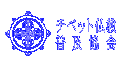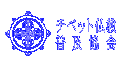『般若心経』は、仏陀の教えとして、方便と智慧の両側面を説くものです。方便の側面は、「広大な行」の修道論として整理され、大慈悲や菩提心の実践が中心となります。智慧の側面は、「甚深な見解」の哲学として整理され、空性や縁起の理解が中心となります。仏道修行にあたっては、方便と智慧の両面を実修することが重要であり、どちらか一方だけでは、目的を達することができません。例えば、空性を本当に理解するためには、数多くの功徳を積むことが求められ、大慈悲や菩提心の実践はどうしても欠かせません。また、実践を正しく続けてゆくためには、正邪を判別する能力が必要であり、そのために空性の理解は不可欠です。
仏教の思想哲学は、説一切有部・経量部・唯識派・中観派という四学派に整理されます。哲学上の諸課題について、各学派はそれぞれ特色ある見解を説いており、ときには少し極端論に陥っている場合もあります。究極的な真理である空性についても、こうした思想哲学の立場から、ある程度概念的な説明が可能です。しかし、空性を完全に体得するためには、修習の積み重ねによるしかありません。
『般若心経』は、古代インドの王舎城と霊鷲山で、釈尊が加持した教えとして説かれています。つまり、舎利拂尊者と観自在菩薩の間で交わされた問答の中身を、後で釈尊が正しいと認めたという意味です。その説法の場へは、普通の人間のみならず、諸菩薩、諸天、八部衆など、様々な所化が集まったといいます。釈尊は深い三昧に入り、その力で舎利拂尊者と観自在菩薩を加持したので、両者の間で空性を主な課題とする問答が始まったのです(この箇所は、玄奘訳に相当する部分がない)。
では、「空性」とはどういう意味でしょうか。まず、「様々なものが実際にあるのか、ないのか」といえば、それらはもちろんあります。しかし、「独立した実体として存在するのか、それとも他のもの(例えば、原因と条件、部分、名称など)に依存しているのか」といえば、後者の見解が正しいのです。そのような在り方を「縁起」といい、その場合の実体性の欠如を「空」といいます。そして、諸存在が究極的に空であるという真理を、「空性」というのです。
そこで、『般若心経』の「色即是空」の意味を考えてみましょう。仏教用語でいう「色」、つまり物質的なもの(色)は、もちろん存在します。しかし、独立した実体として存在しているのではありません。例えば、人間の身体の場合、他者である父母の精子や卵子に依存しています。また米の収穫は、原因としての種子、条件としての水や肥料や人手に依存しています。
もっと深く考えれば、あらゆる存在は、心との関連なくして成立し得ません。つまり、心によって概念化して名称を付与するという過程に依存してこそ、初めてその存在性が確立されるのです。これは、鏡に依存して像が生じるのと同じようなものでしょう。「鏡の像が、実際にそこへ存在している」と一瞬思い込んでしまうのは誤解であるのと同様、あらゆる存在を独立した実体だと認識する心は、正しくない妄分別に過ぎません。こうした心の無知を、仏教用語では「無明」といいます。
私たちが何らかのものと遭遇したとき、心によって名称や概念を付与してから、「これはこれだ」と分別する認識が生じます。こうした分別が、心による名称や概念の付与という過程を経ずして、自然に生じることはあり得ません。例えば、火で湯を沸かすとき「まだ水だ」とか「もう湯が沸いた」などと分別するのは、私たちの心による概念化と名称の付与に過ぎず、それから独立した形で水として、或は湯としての実体が存在するわけではありません。あらゆる存在は、「心によって仮に設定された」という程度のものとして成立しているのであり、それ以上に確固たる実体性を追求しようとしても、結局何も得られないのです。これが、「色即是空」の空という意味です。
このように、空の意味は実体性の否定にほかならず、その実体性のことを仏教用語では「我」と呼んでいます。従って、空は「無我」といい替えることもできます。この無我には、人無我と法無我という二つの側面があります。「人無我」とは、人格的な存在に於ける実体性の否定です。一方「法無我」とは、あらゆる存在に於ける実体性の否定です。いずれにせよ、絶対的な存在性を否定することこそ、釈尊が二つの無我を説いた意味だと思います。
日々の生活の中でも、「もし、物事が独立した実体として存在するならば、どうなるだろうか」とか、逆に「心によって仮に設定されただけならば、どう存在するだろうか」とか、或は「両方の組み合わせならば、どうだろうか」ということを、私たちは経験に照らし合わせながら考えるべきです。物事が自ら独立した実体として存在しているという感覚があるからこそ、それに対する執着や怒りも生じてくるのです。その感覚を弱めることができれば、様々な煩悩を断ち切ってゆけるでしょう。それゆえ、仏道修行を通じて克服すべき課題は、自分や他者という人格的な存在を実体視する「人我執」、及びあらゆる存在を実体視する「法我執」の二つにほかなりません。
過去・現在・未来の三世に数多くの仏陀が出現して教えを説いても、覚るべき究極の真理としての空性には何の変化もありません。「三世諸仏依般若波羅蜜多故、得阿耨多羅三藐三菩提」という経文が、この点を表わしています。つまり、一切の仏陀は、空性を体得する智慧を完成させることにより、覚りの境地を得たのです。チベット仏教の修行とは、空性の体得を目指して、論理的な思考を磨き、慈悲と菩提心を実践しながら、経典や論書を頼りに中観哲学の心髄を極め、それを瞑想や実生活に生かしてゆくことです。空性の本当の意味は、言葉で説明できないほど深遠です。しかし、これを体得するには、まず概念的な理解を正しく確立しなければなりません。それをもとにして修習を重ね、日常生活の様々な局面で経験を積むことにより、本当の理解が得られるのだと思います。
しかし今は、より分かりやすくするため、少し粗い次元で説明を試みてみましょう。私たちが物質の色彩や形状を見るとき、その対象が自分の心に顕現します。知人の姿を見れば、「昔から知っているあの人が、向こうからこちらへやって来る」という概念が瞬時に生じるでしょう。もし、その人が「知人」という実体として成立しているならば、容姿などの特徴を見分けられるよりも以前の段階から、知人であることを判別できるはずです。それが不可能なのはなぜかといえば、視覚から得られた容姿などの情報が、意識に記憶されている知人の情報と合致したとき、初めて「あの人だ」という分別が生じるからです。つまり、視覚や記憶に頼った概念化を通じて仮に設定されたという程度の存在感をもって、「知人」は成立しているのです。それ以上に堅固で確かな実体を、視覚で捉えた知人の顕現のどこかに見いだそうとしても、得られるものはありません。これは、空性や無我を粗い次元で理解するための、一つの例です。
しかし、空性という究極の真理は、あらゆる存在に於て等しく平等なものだから、ある一つのものに関して空性を本当に理解できれば、全てそれと同じだということになります。この空性と表裏一体の関係として、あらゆる存在が他のものに依存して成立しているという「縁起」を理解することも重要です。「物質的な存在には、心によって仮に設定された以上の実体性がない」ということが、「色即是空」の意味です。一方、「そうした物質的な存在の究極的真理である空性は、縁起によって物質として顕現する」ということが、「空即是色」の意味です。「物質的なもの以外でも、心そのもの(識)や心の働きなど(受・想・行)、全て同様である」というのが、「受想行識亦復如是」の意味です。
空性と縁起は表裏一体なので、縁起について正しい理解を確立すれば、空性を間接的に理解できます。縁起の分かりやすい意味は−前に米の収穫の例をあげたように−「あらゆる事物が、原因と条件に依存して成立している」ということです。原因や条件に依存して初めて成立し得るならば、そこに独立した実体性を見いだすことはできません。縁起のより深い意味は、「あらゆる存在が、部分に依存して成立している」ということです。「人間という存在の実体は、どの部分にあるのだろうか」と追求していっても、結局何一つ得られません。
このように分析を深めてゆく過程で、唯識派の場合、「あらゆる存在は、外側の対象として成立しているのではなく、ただ心によって引き起こされた顕現に過ぎない」という見解を主張しています。一方、中観自立論証派は、「外側の対象と内側の心という両方の力によって、あらゆる存在は成立している」と主張しています。しかし、「外側の対象としてある程度成立している」という点を厳密に分析してゆけば、どこにもその実体性を見いだせません。それゆえ、中観帰謬論証派の場合、「あらゆる存在は、名称の付与を通じ、心によって仮に設定されたものに過ぎない」という立場をとっています。外側の対象の実体性を完全に否定し、「心によって仮に設定されたものに過ぎない」とするこの見解は、しかしながら、唯識派のように「外側の対象が存在せず、心の反映に過ぎない」と主張しているわけではありません。「実体として成立すること」と「単に存在すること」を明確に区別し、前者を否定しつつ後者を認めるという点が、中観帰謬論証派の見解の特色です。それによって、外側の対象を実体視する「実在論」や、逆に全くの無とする「虚無論」という、両極端の立場から離れることができるのです。これが、「中道」の意味にほかなりません。
では、唯識派や中観自立論証派の見解は有害なものなのかといえば、そうではありません。これらの見解も、究極的な真理を理解するための段階であり、釈尊が巧みな方便によって説いた教えに由来しています。また、私たちの自然な思考形態が、これらの見解に少しづつ反映されているとも考えられます。
私たちは、長年に渡り積み重ねてきた経験的な心の働きをよく分析し、そのどこに問題があるのかを知らなければなりません。つまり、自分の心の中にある無明の正体を突き止め、どういう点が正しくないかを明らかにするのです。まさに無明とは、人我執と法我執にほかならず、この両者を断滅しない限り、解脱や覚りを得ることはできません。人我執や法我執をはじめとする諸煩悩は、修行を通じて断ち切るべき「煩悩障」です。この煩悩障を断った後にも、「所知障」が潜在余力として残り、それによって外側の対象が実体性を伴って心に顕現します。この所知障をも完全に断ったとき、一切智たる仏陀の境地が実現するのです。
仏道修行とは、自らの心を高めてゆく過程です。現在の粗い心を断滅し、心の真の在り方に迫れば、その本質である空性−光明−と出会うことができます。心の本質は純粋なものですが、未だ智慧や正しい経験を伴っていません。それらを獲得するには、自分自身の努力が不可欠です。正しい道に従って精進し、智慧や経験を積み重ねてゆけば、無明の闇は少しづづ除かれてゆきます。現在の誤った心の働きをよく観察し、それを修正しながら次第に体験を深めてゆけば、いつか仏陀の覚りを得られるでしょう。そのためには、まず教えを学び、検証して理解を深め、それから実践するという手順が欠かせません。
仏・法・僧の三宝にも、独立した実体はありません。釈尊も、私たちと同じ凡夫の状態から修行を始め、大変な努力を積み重ねた暁に一切智を得たのです。それゆえ、私たちも釈尊を見習って修行に励めば、やがて仏陀の境地へ辿り着くことができるでしょう。そのための道には、最初に述べたように、方便と智慧の両面があります。
これまで智慧の面について少し説明してきましたが、空性の意味を「全く何もないこと」とか「絶対的な無」と捉えてはいけない点を、いま一度確認しておきましょう。もし、そのように誤解してしまうと、仏陀の様々な教えと矛盾するし、方便の道も成立しなくなります。かといって、逆に「独立した実体としてある」という立場も、もちろん正しくありません。日常生活で「ある」とか「ない」とか簡単にいいますが、仏教哲学から考えると、両極端の立場を排除しつつ有無という概念を設定するのは、実に微妙な問題なのです。これは、心による認識の状態を正しく把握することで、初めて的確に判断できるでしょう。認識対象は、私たちの心に顕現しているとおりのものとしてあるわけではなく、さりとて全くの無でもなく、その中間に「存在」というものは設定できるのです。
外側の対象が心に顕現するとき、私たちはつい「対象自体の力によって、そうなっている」と思い込み、それに対して様々な煩悩などを起こしたりします。しかし、対象の真の在り方は、外側から物理的に追求しても、決して正しく理解できません。そうではなく、対象を認識する心に分析を加え、その成果を反映しながら智慧に磨きをかけることで、少しづつ明らかになってくるのです。
このように、存在や空性の意味は非常に微妙で難解なので、簡単に説くことはできません。釈尊は深い三昧に入って舎利拂尊者と観自在菩薩を加持し、その結果で両者が問答を交わし、それを通じて明かされた空性の義を釈尊が追認します。そのような形式で、『般若心経』は説かれているのです。
その中で、観自在菩薩が最初に空性の義を提示する際の表現は、「五蘊それぞれに於ても、自性は空であると、正しく観じなければならない」というものです(この箇所は、玄奘訳に相当する部分がないけれど、「照見五蘊皆空」と意味は同じ)。つまり、「物質的なものをはじめ、あらゆる事物には、実体がない」という意味です。それ以下の経文では、「空中無色、無受想行識、無眼耳鼻舌身意…」というふうに、「五蘊、十二処、十八界、十二縁起、四諦、智、得不得など、全てない」と説かれていますが、これらは「実体がない」、或は「究極の真理として成立しない」という意味で理解すべきです。決して、「五蘊などが全く存在しない」と誤解してはいけません。「色即是空」も、「原因と条件に依存しないような、独立した実体としての物質など、厳密に分析して追求すれば存在しない」というふうに換言すれば、少し分かりやすいでしょう。
こうした空性は、究極的な真理なので、物質的な存在に於てそれを理解できたら、あらゆる存在に適用可能です。修行のテーマとなる十二縁起や四諦に於ても、全く同様です。十二縁起などを観じる瞑想を繰り返せば、確かに修行の効果もたらします。しかし、それらに存在としての実体性があるのかといえば、どこにも見いだせません。
ところで、『般若心経』の後半には「羯諦羯諦…」という咒が説かれていますが、チベット仏教では、これを密教の真言だとは位置づけていません。この咒は、『般若心経』の説く真実そのものを、短い梵語に凝縮して表現したものです。「是無上咒、是無等等咒」という経文は、「究極の真理である空性を表現する言葉」という意味に理解すべきでしょう。
この咒は、修道論の立場から解釈することもできます。最初の「羯諦」は資糧道を越えること、次の「羯諦」は加行道を越えること、「波羅羯諦」は見道を越えること、「波羅僧羯諦」は修道を越えること、そして「菩提薩婆訶」は無学道を象徴しています。こうした大乗の五道は、菩提心を発して菩薩行を積み、我執をはじめとする諸障を粗大なものから順に断滅し、その結果として仏果を証するまでの過程にほかなりません。
観自在菩薩がこの咒まで説き終えると、釈尊は深い三昧から立ち、舎利拂尊者と観自在菩薩との問答を「善いかな、善いかな」と承認します。つまり、三昧の中身と問答とが、完全に一致するということです(この箇所も、玄奘訳に相当する部分がない)。
究極の真理である空性は、言葉による説明だけでは、容易に理解し難いと思います。それゆえ、日常生活の経験的感覚を厳密に分析する習慣をつけておくことも、空性理解の一助になるかもしれません。私たちは、「自分というものが、どこかに独立した実体として存在する」という我執の感覚があるからこそ、貪欲・怒り・愚かさという三毒を生じるのです。こうした我執は、単に個人の煩悩だけでなく、社会や国家などのレベルで様々な問題を引き起こします。ある人が怒りっぽいのも、集団としての意思や行動がヒステリックになるのも、原因は我執にあります。独立した実体として誤認された我を守るため、そのように激しい感情が生じてくるのです。そうしたときはいつも、巨大化された我が、心の中で台頭しているはずです。だから、日常の次元でも、愛着の対象である我の正体を見極め、その存在を過大視することの弊害を知るべきです。
例えば、強い怒りで顔が赤くなるとき、本当は外側からの影響でそうなっているのではありません。心の状態が変化し、どこかに強烈な我が出てきたため、それが身体に影響して顔が赤くなるのです。このとき、私たちは「自分が怒っている」と感じるわけですが、その「怒っている自分」がどこにあるのかを追求してゆけば、結局何も求められないでしょう。強い怒りや喜びなど極端な感情が生じているときは、普段感じられない強力な我を把握しやすい状況にあります。その機会を捉えて、「いま感じた我は、どこにあるのだろうか」と、徹底的に分析を加えてゆけば、我に実体のないことを理解できるはずです。これは、日常生活の中で無我の教えを知る絶好のチャンスです。
「自分という存在は何か」という点を真剣に考察し、我執や自己愛着を少しづつ弱めることができれば、それは他者を尊重する立場へつながります。自他の関係を冷静に考えれば、決して自分が全てではなく、他者に依存して自分が成立していることも理解できます。
また、あらゆる存在が心によって仮に設定されたものに過ぎないという点を、生活の中で比喩的に知る方法もあります。例えば、書物を読むときです。チベット語の表音文字は、それ自体の意味を持っていません。そのような文字を組み合わせて綴り、単語の発音を表現するプロセスを繰り返して−つまり、心による概念化を積み重ねて−書物の中身を知ることができます。しかし、その中身を、単なる符号の羅列に過ぎない文章の中から−概念化という過程を経ず−直接つかみ取ろうとしても、それは不可能です。このようにして、空性の意味を−経典の学習だけでなく−日頃の生活の中でも捉えてゆくように心がけましょう。
無常という側面から、空性理解に迫ることもできます。無常とは、刹那に変化してゆくことです。過去の自分と現在の自分は、同じでありません。今の刹那の自分は、前刹那の自分を含めた様々な原因と条件によって、この刹那に成立したものです。こうした点から、誕生以来続いてきたかに思える「自分」という概念には何の実体性もないことを理解できるでしょう。この刹那という概念を無限に微細化してゆくことで、空性理解も深まるはずです。
そのようにして、空性理解をひたすら深めてゆけば、やがて言葉や概念で説明できない状態へ至ると思います。その境地は、深い三昧を通じて、直感的に会得するしかありません。これこそ、『般若心経』の「開経偈」としてチベットでよくお誦えする「不可説にして不可思なる甚深般若波羅蜜で、不生不滅と空性の二諦を証して覚るべし」という意味なのでしょう。